そのユーラシア大陸の中央部をまとめたのがイスラーム文明だった。
ヨーロッパも中国も、インドも北アジアの遊牧民もイスラームと接触した。
そのわりに中学高校の世界史でも、世間一般の認識でも、
イスラーム世界の歴史についてはよく理解されていないように思う。
そんなイスラーム世界の歴史についてダラダラ語ってみようと思う。
笑い系か真面目系か、どういうスタンスで語るか、いまいち決められてない。
あれはイスラムとヨーロッパのミックスだからな
今んとこ誰も見てないだろうけど、ダラダラ書いていこう。
(ブロットも決めてないから流れ任せで)
まずはイスラームが成立した時代の状況から。
イスラームという宗教は、西暦622年頃にアラビア半島西部の
メッカに住んでいた商人ムハンマドが創始したとされている。
実はその少し前から、ユーラシア大陸の西半分では、
当時のレベルで「世界大戦」と言える規模の大戦争が続いていた。
一方の雄はゾロアスター教を国教とし、インダス川から地中海までの支配を目指すササン朝ペルシア。
もう一方の雄は、これに対抗して古代ローマ帝国の復興、地中海再統一を目指す東ローマ帝国。
アラビア半島は両大国の中間にあったけど、灼熱の砂漠が広がっているので直接戦場にはならない。
その代り、両大国はアラビア周辺の小国を煽って代理戦争をやらせた。
ササン朝ペルシアはアラビア半島東部のオマーンに侵攻し、
南部のイエメンにあった小国群を従属させて、東ローマと東洋を結ぶ紅海航路を遮断しようとした。
それに対して東ローマ帝国はアフリカ島北部のエチオピアを煽って、アラビア半島に侵攻させた。
エチオピアの将軍アブラハはイエメンに渡り、そこからアラビア半島西岸を攻め上った。
ところが、途中のメッカまで来たときに、突然疫病が流行って兵士がバタバタ倒れたので退却した。
メッカの人々はアブラハの軍が見たこともない巨大な動物、象を連れているのを見て驚いた。
そこでアブラハがやって来た年は「象の年」として語り伝えられた。
この年に、メッカの商人アブドゥッラーの子としてムハンマドという子供が生まれた。
西暦570年のことと言われている。
ローマ好きの自分にとってイスラムの番狂わせ感は異常
母親も生まれて数か月後に死んでしまったので、
爺さんと叔父さんに育ててもらった。
青年になったムハンマドはハディージャという女商人に仕えることになった。
真面目で顔も性格も良かったのでハディージャに非常に気に入られ、ついに婿になる。
この時ムハンマドは25歳、ハディージャは40歳ぐらいだったらしい。
そんな年の差にもかかわらずムハンマドはハディージャをとても大切にした。
610年頃。
結婚生活15年目、40歳を迎えたムハンマドは人生の意味などについていろいろ悩みを生じたらしく、
メッカの近くの岩山の洞窟で瞑想にふけることが多くなった。
仕事をサボっていたのかどうかは知らない。
そんなある日、彼はふと「読め!」という叫び声を聞いて目を上げた。
すると地平線上に巨大な巨大な人影が立っている。東西南北、どの方向にも巨大な人影が立っている。
巨大な人影は「天使ジブリール」(ガブリエル)と名乗り、「神の啓示を読め!」と命令する。
ムハンマドは暑さのあまり頭がやられたかと慌てて家に飛びかえり、
ハディージャ(65)の膝に縋り付いて震えた。
そこでムハンマド(40)もだんだん自信を持って、天使が告げる言葉を周囲の人々に述べ伝えるようになった。
その頃アラビア、というか西アジア全体で自称預言者はいくらでもいたとはいえ、
やはり周りから見れば気が触れたとしか見えないので、最初のころは誰も相手にしてくれなかった。
最初の信者になったハディージャを除くと、かろうじて親友中の親友アブー・バクルと従兄弟のアリーだけが信じてくれた。
ときには遠くの町に行って説教もしたけど、相手にされないばかりか石を投げられた。
とはいえ石の上にも三年、石を投げられても三年で、じわじわと彼の言葉に耳を傾ける者も出てくる。
メッカの長老たちはムハンマドを「若者を煽動する危険人物」とみなして暗殺計画を立てた。
それを察知したムハンマドは夜陰に紛れて、支持者のいる北方の町、メディナに逃走した。
なお、暗殺者たちをかわすためにムハンマドの寝床にはアリーが代わりに横になり、
襲ってきた刺客たちを軽く撃退してからムハンマドの借金を全部代わりに返済して、後から師匠を追っかけて行った。
ハディージャはこの時点で亡くなっていた。
これが西暦622年。イスラーム暦の元年になる。
「公平な第三者」として巧みに仲裁し、いつの間にかメディナの指導者になった。
ここから預言者ムハンマドの政治家・軍人モードが発動しはじめる。
まずはメッカの隊商妨害。
メッカと北方シリアをつなぐ隊商ルートを何度も襲撃してメッカの経済力をすり減らす。
襲ってきたメッカの正規軍を迎え撃って見事に撃退。
近隣の遊牧民たちを次々に服従させ、やがてムハンマドの威令はアラビア半島全土に轟くようになる。
その過程では盟友アブー・バクルやアリーも大いに協力した。
そして632年。
苦節10年を経てついにムハンマドはメッカに再入城する。かつて自分を追放した町に、今度は征服者として。
メッカの中心、無数の偶像が祭られたカアバ神殿に入ったムハンマドは弓を構え、
「真理が来た! 真理が来た! 今や暗黒は去った!」と叫びながら、次々に偶像を射倒した。
最後に、神殿中央におかれた真っ黒な隕石だけが残った。
ムハンマドはこれを神アッラーの象徴として永遠に残すことにした。
アラビア全土から様々な部族がメッカに代表を送り、ムハンマドに忠誠を誓った。
ムハンマドは北方でなおも「世界大戦」を続ける東ローマ帝国とササン朝ペルシアにも使節を送り、イスラームへの改宗を勧めた。
ところがササン朝ペルシアに行った使節は「砂漠の蛮族が何をほざくか」と鼻で笑われ、
頭に砂をかけられて舞い戻って来た。
それを聞いたムハンマドは喜んでこう言ったという。
「ペルシア王は我らに返礼として土を贈った。ペルシアの国土が我らの物となる証拠である」
それから2年度、ムハンマドは重病となって、晩年に迎えた幼な妻アーイシャの膝で死んだ。
634年のことだった。
まず、後継者をどうするか。
ムハンマドの生前はどんな問題が起こっても、彼が「神の言葉」で教団を導いた。
ところが彼が世を去った今、「神の言葉」を聞くことができる人物はいない。
ムハンマドには息子もいなかった。ファーティマという娘がおり、その婿が従兄弟のアリーだったが、
アリーは「私はまだ若く、教祖の後継者にはなれない」と遠慮した。
話し合いの結果、ムハンマドの親友だったアブー・バクルが中心となって、合議で教団を運営していくことになった。
もう一つの問題はいっそう深刻だった。
アラビア半島の諸部族はムハンマドという特異なカリスマと軍事的才能を持つ預言者に従っていたのであり、
ムハンマドが死んだとたんに「ほな知らんわ」と一斉に離反してしまったのだ。
アブー・バクルを中心とするイスラーム教団は生き残りのために、
アラビア半島全体をもう一度征服しなおす羽目になった。
このとき、ハーリドという武将が鬼神のような活躍を繰り広げる。
ハーリドは生前のムハンマドに「アッラーの剣」と讃えられた名将だ。
ムハンマドより年上だったアブー・バクルはわずか2年後に病死。
次にウマルという人物が教団の指導者になった。
その頃、ハーリドらの活躍でアラビアの再統一はほぼ成っていた。
前線で戦っている軍団の動きはメッカにコントロールしきれなくなってきた。
彼らはその場その場の状況に応じて、あるいは目先の戦利品を目指してどんどん戦線を拡大した。
その結果、際限なく「世界大戦」を続けていた北の大国、ササン朝ペルシアと東ローマ帝国の国境に
突然砂漠の蜃気楼の彼方からアラブの遊牧民たちが乱入することになる。
東ローマ皇帝ヘラクレイオスはアルメニア・突厥・ハザールといった
周辺国と大連合軍を組んでササン朝ペルシアの本国イラクに侵入し、
首都のクテシフォンを包囲して、灌漑施設を破壊しまくった。
そのせいでメソポタミア文明以来の農業基盤はガタガタになった。
一方、ササン朝ペルシアのホスロー2世は同じタイミングで
東ローマ帝国領のシリア・エジプトを襲撃し、
皇帝不在の首都コンスタンティノープルを急襲した。
大帝国の皇帝二人が最前線に出て、まったく同時に
互いの首都に王手をかけるというカオスな状況。
東ローマ皇帝ヘラクレイオスは慌ててシリア・エジプトからペルシア軍を叩き出し、
なんとか講和が成立したものの、この激闘で両国とも軍事的・財政的に疲弊しきった。
そこに突然第三勢力が湧いて出たからたまらない。
あれよあれよという間に、アラブ・イスラーム軍は南イラクを占領し、シリアに進撃した。
このとき前線の総指揮官だったのが例の名将ハーリド。
ハーリドがシリアに侵攻すると、東ローマ皇帝ヘラクレイオスは
「俺が人生の半分かけて取り戻したものを奪われてなるか」と迎撃に出るが、見事一蹴される。
このときヘラクレイオスは、「シリアよさらば、敵にとってなんと美しい国なのか」と嘆いた。
帰途、彼は落胆のあまり精神を病み、水を見るのが怖いという謎の病気にかかった。
首都コンスタンティノープルに入るときにどうしても海を渡らないといけないので、
四方を板で囲った船を造らせて何とか都に入ることができたという。
ところが、勝者の側にも悲劇が見舞っていた。
勝利の立役者ハーリドは、メッカで教団を指導しているウマルと仲が悪かった。
東ローマ軍との決戦前夜、ハーリドのもとにウマルからの命令書が届いた。
静まり返った天幕の中で、ハーリドは一人その文書を開いた。
そこには、「おまえクビwww」と書いてあった。
ハーリドは何も見なかったふりをして、翌日の決戦で見事大勝利した。
敗走する東ローマ軍が地平の彼方に消えて行った後、ハーリドは部下たちを集めて
無言でウマルの命令書を取り出して見せた。
誰もが声を失うなか、ハーリドは表情ひとつかえずに姿を消したという。
熱い展開が続くな
アブー・バクルやウマルは「カリフ」(正確にはハリーファ)と呼ばれる。
アラビア語で「代理人」って意味。
「アラブの大征服」と言われる、世界史を変える戦争は始まったばかりだった。
637年、アラブ軍はササン朝ペルシアの首都クティフォン(バグダッドの近く)を占領した。
王宮の宝物庫には膨大な金銀財宝があったが、アラブの末端の兵士たちは金など見たことがなかったので、
大量の金を自分たちにも価値が分かるちょびっとの銀と取り換えて悦に入っていた。
防虫用の樟脳は塩と間違えて、神妙な顔をして「文明の味」を堪能したという。
シリアではハーリドが去った後、アムルという武将が頭角を現してきた。
「神の剣」ハーリドとは対照的に、知略で勝負するタイプの名将だ。
彼が聖都エルサレムを陥落させると、カリフのウマルが前線に視察に来た。
その頃のカリフたちはとても質素だったので、ウマルは従者も連れずにロバでやって来て、
粗末な皮の服を着たまま地べたに額づいて神に感謝したという。
さて、アムルはウマルをつかまえて、こう進言した。
「なんでもちょっと西の方にエジプトとかいう大変豊かな国があるらしいんですが」
「ああ、じゃあ征服したまえ」とウマルは簡単に許可した。
ところがメッカに帰ったウマルは気が変わってきた。
「エジプトとか、さすがに本国から遠すぎるんじゃね?」
さて、エジプトに向けて進軍を開始したアムルのもとに、
ある夜カリフ・ウマルからの密使がやってきた。
アムルは密使に渡されたウマルの命令書を凝視した。
彼のなかで何かの直感が動いた。
彼は命令書の封を開けずにそのまま進軍を続け、翌日にエジプト国境を越えた。
その夜、彼がウマルの命令書を開封するとこう書いてあった。
「もしお前がこの手紙をエジプトに入る前に開封したなら直ちに引き返せ。
エジプトに入った後に開封したなら、後は運命をアッラーに任せよ」
彼は運命をアッラーに任せて東ローマ帝国の守備隊を追い払い、エジプトを征服した。
箇条書き的にすると、こんな感じで「アラブの大征服」は怒涛のように進む。
632年 ムハンマド死亡(さっき書いた634年ってのは間違い)
635年 ダマスカス占領
636年 ヤルムークの戦い(シリア征服)
637年 クテシフォン占領
639年 エジプト侵攻
642年 ニハーヴァンドの戦い(ササン朝ペルシア崩壊)
そして644年、ウマルはメッカで死亡する。
次にカリフになったのはウスマーンという老人だった。
ウスマーンは信仰心が深かったが、リーダーシップを取るタイプではなかったので、
何も知らない能天気なカリフのお膝元で汚職が横行し、政治が混乱し始めた。
やがて不満を持った兵士たちがウスマーンを襲って殺害する。
イスラームの歴史上最初に、信者がカリフを殺した事件だった。
ウスマーンの殺害者たちはメッカに残っていた有力者たちのなかで、
いちばん筋目が正しいアリーを次のカリフに担ぎ出した。
ムハンマドの従兄弟かつ娘婿で、世界で2番目にイスラームの信者になった例の豪傑だ。
ところが、その頃シリアを支配していたムアーウィヤという総督がこれに反対する。
「カリフを殺した連中が擁立したカリフなんて認められっかよ。俺は忠誠の誓いを拒否すんよ」
こうして「第一次内乱」といわれる内部紛争が始まった。
アリーは今や前線から遠く離れたメッカを離れ、イラクに拠点を移した。
そこで多くの6万人もの兵士を集めて、シリアの総督ムアーウィヤに戦いを挑む。
戦いはアリー優位に展開したが、突然ムアーウィヤ軍の兵士が
槍の穂先に聖典コーランを結び付けて振りかざした。
「お前たち、アッラーのお言葉が書かれた聖典に向かって武器向けるの?
バカなの? 死ぬの? 地獄行くの?」
ってわけでなし崩し的に停戦に追い込まれたアリー。
「ばかじゃねーの」と憤慨して出ていった過激派は「あんな無能が諸悪の根源」と逆切れし、
礼拝中のアリーを襲って滅多切りにした。カオスである。
(ムアーウィヤの暗殺も計画したが失敗)
以後、アリーの支持者たちは「シーア派」、それ以外は「スンナ派」と呼ばれて
イスラームの二大宗派を形成する。
ウマル、ウスマーン、アリーの4人がカリフとして教団を指導した。
彼らの指導のもとで(と言いながら前線の独走がほとんどだけど)
教団の勢力はアラビア半島西部から、東はイラン、西はエジプトまで拡大した。
彼ら4人を、イスラームがシーア派だのスンナ派だのに分裂する前の
古き良き時代のカリフたちとして、後世「正統カリフ」と呼ぶことになる。
アリー殺害によって正統カリフ時代は終わり、イスラーム世界は大きく動揺した。
敵が勝手に自滅したシリア総督ムアーウィヤはついにカリフを自称し、
シリアのダマスカスを拠点にイスラーム世界を再統合した。
ムアーウィヤはイスラーム史上初めてカリフの座る玉座や謁見の間を用意し
一般人と自分を隔離した。
ここにきてカリフは単なる「教団指導者」から「皇帝」に近い存在になったのだ。
ムアーウィヤは自分の息子ヤズィードを後継者に決めて、世襲の王朝を開いた。
「ウマイヤ朝アラブ帝国」の誕生だ。
正統カリフたちはみんな自分で後継者を指名せず、死後の互選に任せた。
自分の息子を優遇することもなかった。
当然ながら「教団の私物化だ!」と批判する人々も多いだろう。
臨終の際にムアーウィヤはヤズィードを呼んで、こう遺言した。
「いいか、アリーにはフサインという息子が生き残っている。
フサインには決して手を出すな。もしフサインを殺したりしたら大変なことになる」
ところがヤズィードは遺言を守らなかった。
ウマイヤ朝に反対する人々は多い。
イラクのクーファという町の人々は、アリーの遺児ヤズィードを旗頭に反乱を起こそうとして、
メッカにいたフサインを招いた。
フサインは権力争いを嫌って何度も謝絶したが、とうとう断り切れずに旅立った。
ヤズィードは慌てて3000人の軍隊を派遣してユーフラテス川の畔でフサインたちを包囲した。
フサインと従者は合わせて72名。
目の前に川があるのに周囲を3000人に囲まれ、絶望のデスゲーム。
飢えと渇きの1週間が過ぎたあと、一瞬の虐殺が展開され、ムハンマドの孫は殺された。
これが「カルバラーの悲劇」と言われる事件。
これをもって、アリー支持者のシーア派と、その他多数派のスンナ派の対立は決定的になる。
シーア派はウマイヤ朝の権威を否定し、ムハンマドとアリー、フサインの子孫こそが真の指導者だと主張し、
その後何度も反乱を起こすようになる。
初代正統カリフ、アブー・バクルの孫が「自分こそマジカリフ」と主張し、
イスラーム世界の南半分を制圧。
これに対して、ウマイヤ朝は「ハッジャージュ」という冷酷無比な将軍を送り込む。
ハッジャージュは敵軍の本拠地メッカを包囲し、遠慮会釈なしにガンガン投石した。
聖都はボロボロに破壊され、カアバ神殿も瓦礫になるも反乱は平定された。
ついでハッジャージュはシーア派の拠点、イラクのクーファに乗り込んだ。
黒い覆面で顔を隠し、礼拝の真っ最中に突然モスクに登場。
ズカズカと説教壇に上り、あっけにとられる群衆を前に演説をぶった。
「ターバンの下に血が流れる。我こそはそれを実現する者である!」
ハッジャージュが覆面をはぎ取った瞬間、兵士たちが雪崩れ込んで、
モスクに集まっていた群衆6万人を皆殺しにしたという。
ハッジャージュはウマイヤ朝のカリフに絶賛され、帝国東半分の全権を任された。
そこで彼は「大征服」をさらに進めることにして、腹心の部下二人に命じた。
「クタイバは中央アジアに進め。カーシムはインドに進め。
どちらかより早く中国に到達した者を中国全土の総督にする」
ちなみに二人ともそこそこの成功はおさめるものの、
カリフが代わると強すぎる力を持ったハッジャージュは危険視されて処刑され、
クタイバとカーシムも巻き添えをくらって終わる。
中国とイスラーム世界の衝突はもう少し先になる。
この頃、西側でも大征服は一段と進む。
エジプトから西へ西へと進んだウマイヤ朝軍は709年についに大西洋に達した。
指揮官はモロッコ西端まで来ると、海に馬を乗りいれて、
「アッラーよ、これより先にもはや征服すべき土地はないのですか!」と絶叫したらしい。
まだあった。
その頃、モロッコの北のイベリア半島(スペイン・ポルトガル)にあったキリスト教の西ゴート王国では
国王ロドリーゴが、国境の要塞を守るフリアン伯爵の娘に一目ぼれして、彼女をレ○プしてしまった。
伯爵は激怒して、復讐のためにウマイヤ朝軍を呼び込んだ。
711年にウマイヤ朝の将軍ターリクはイベリア半島に上陸し、わずか7年でイベリア半島全土を制圧した。
イベリア半島最北端の山岳地帯に辛うじて西ゴートの残党が逃げ込んで、
ここから「7年で奪われたものを700年かけて取り戻す」国土回復戦争が始まることになる。
一人の伯爵が歴史を変えたんだな
繰り返すが、ウマイヤ朝に反対する人々は多い。
大征服は景気よく進んだものの、内政はうまくいかなかった。
アラブの部族同士の対立、先祖代々の信者と新参信者の対立、
戒律をガン無視して酒は飲むは絵は描かせるわ(イスラームは絵画禁止)の
ウマイヤ朝カリフたちに対する感情的な反発。
そんな状況の中、世界の歴史でも稀にみる規模の陰謀劇が始まる。
730年頃、今のヨルダンの近くの砂漠の中に、ムハンマドの叔父の
「アッバース」の子孫たちが隠れ住んでいた。
彼らはウマイヤ朝への不満の高まりを見て、「もしかすると俺らにチャンスが」と直感。
各地に密使を派遣して反乱を煽動することにした。
そんな密使の中に「アブー・ムスリム」という、謎に満ちた人物がいた。
彼のことは本当に分からない。
まず「アブー・ムスリム」は本名ではない。あだ名みたいなもの。
出身地も分からない。前半生も分からないし、民族すら分からない。
とにかくアブー・ムスリムはアッバース一族に命じられ、身一つで中央アジアに潜入した。
そこで彼は、ありとあらゆる反体制勢力を舌先三寸でまとめ上げた。
どの勢力にもいい顔をして、自分の背後にいるアッバース一族の存在は完全に秘密にして、
ただ「皆が満足する者をカリフにしよう」と玉虫色の未来を描いてみせた。
なんとも不思議なことに、それだけでありとあらゆる反体制派が彼のもとに集結し、
たちまち世界を揺るがす大反乱となってイラン、イラクを席巻し、
ついにウマイヤ朝を崩壊させてしまった。
ちなみにこの混乱のなかで、肝心のアッバース一族も巻き添えをくらって殺されてしまう。
アブー・ムスリムは、辛うじて生き残ったアブー・アル・アッバースという人物を探し出し、
突然「皆さん大事な話があります。この人がカリフになります」と宣言した。
それまでアブー・ムスリムに従っていたありとあらゆる反体制派たちは
「なんだそりゃ、聞いてねえ!!」と驚愕したが、なんとなく場の勢いで新カリフが確定。
世にいう「アッバース革命」であり、「アッバース朝イスラーム帝国」の誕生である。
750年のことだった。
「唐」である。
時は西暦751年。
アッバース革命の翌年、唐の将軍「高仙芝」は標高5000メートルのパミール高原を突破し、
ウズベキスタンのタシケントを急襲した。
タシケント王はアッバース朝、正確には中央アジアの実質的な支配者だった
アブー・ムスリムに助けを求めた。
そこでアブー・ムスリムは腹心の部下を派遣し、タラス河畔で唐軍と戦わせる。
唐軍は夜更けの戦いで裏切りが出て総崩れとなり、
高仙芝自身も棍棒を振り回して命からがら逃走した。
この時捕虜になった唐軍兵士の中に製紙職人がいて、
漢代に発明された「紙」というものが初めて大陸西方に伝わることになる。
さて、そんなアブー・ムスリムもお約束の通り、
二代目カリフのマンスールに危険視されて殺される。
アブー・ムスリムは「わ、わたしを生かしておけば必ずあなたの敵を滅ぼします!!」と
命乞いするが、マンスールは「おまえ以上に危険な敵がどこにいる」と言い捨てたという。
その通りですね。
マンスールは、今やユーラシア大陸の半分にまで広がった帝国を支配するのに
ふさわしい土地を探し回り、やがてイラクの中央分の「バグダード」という場所に
新しい都を建設する。
バグダードの中心部は円形の城壁に囲まれ、最盛期には100万人もの人々が住む。
ここに世界中の富と情報が集まり、カリフは密偵や郵便制度を使って、
都にいながらにして世界中のことを知っていたという。
ちなみにアッバース朝というのは非常に専制的で、カリフ絶対主義だった。
カリフの横にはいつも死刑執行人が控えており、カリフの命令一下、
誰の首をも即座に切り落としたという。
彼は「アラビアンナイト」に何度も登場するので有名。
ドラ○もんの映画に登場したことさえあるので、多分日本で一番有名なアッバース朝カリフ。
しかし、史実のハールーン・アッラシードは大した名君とは言えない。
治世前半には宰相一族の操り人形に過ぎなかったし、その宰相のジャアファル
(アラビアンナイトの物語ではハールーンと一緒によくお忍びやってる)が
自分の妹に色目を使ったのにキレて突然宰相一族粛清したはいいものの、
ちょうどそのころから各地で反乱祭りとなり、ハールーン自身、イランの反乱鎮圧中に病死する。
ハールーンの子のマアムーンは大変学問好きで、バグダードに「知恵の館」という施設を作った。
これは図書館と研究所と大学と翻訳センターを兼ねていて、ギリシア・ローマやペルシア・インドなど、
イスラームがそれまで接触・征服したあらゆる地域の古典や学問研究の成果を結集し、
アラビア語に翻訳して後世に伝えるという役割を果たした。
今残っている古代ギリシアのプラトンやアリストテレスの哲学書なんかも、
ほとんどはこの頃アラビア語に訳されたものだったりする。
ギリシア本土やヨーロッパでは文献が散逸してしまったのだ。
しかし政治的には(ry
モロッコのイドリース朝、チュニジアのアグラブ朝、イラン東部のターヒル朝。
帝国は広大すぎた。辺境で次々に地方政権が台頭し、名目上はアッバース朝の
主権を認めるものの、実際には好き放題に自治をするようになる。
たとえていえば、戦国初期の室町幕府に近い。
マアムーンの死後、ムタワッキルというカリフは王朝をたてなおそうと、
「マムルーク」を導入した。
これは中央アジアにいたトルコ系の遊牧民の青少年を奴隷として大量に購入し、
みっちりと軍事訓練を施し、カリフへの忠誠心を植え付けて直属軍にしようという試みだった。
しかし結果として、その後の政治はマムルークたちの思うがままとなり、
歴代カリフは完全にマムルークたちの神輿と化す。
その頃、イラク南部では「ザンジュ」と呼ばれた黒人奴隷の大反乱が起こったり、
「カルマト派」という過激派がメッカを襲撃してカアバ神殿の黒い隕石を強奪したりと
実になんとも滅茶苦茶な政治情勢となっていった。
750年のアッバース革命のときに、シリアにいたウマイヤ朝の王族は皆殺しにされる。
そのとき、たった一人の青年が身一つで脱出し、装身具を売り払って逃走資金にし、
川を泳ぎ山を越えて危地を掻い潜り、アッバース朝の目の届かない遥か西方に逃れた。
彼の名はアブドゥル・ラフマーン。母親が北アフリカのベルベル族で、金髪に青い目をしていたという。
ベルベル族の土地にたどり着いた彼は、海の向こうに豊かな国があると聞いて、イベリア半島に乗り込んだ。
帝国中心からあまりにも遠く離れ、未開の異教徒が跳梁する
「ヨーロッパ」と隣り合うイベリア半島。
この土地でアブドゥル・ラフマーンはみるみる頭角を現し、
次々に都市を占領し、アッバース朝の支配の及ばない独自の王国を築き上げた。
時のカリフ、マンスールはこれを奪還しようとするが、
アブドゥル・ラフマーンはアッバース朝軍を撃破したばかりか、
その指揮官の首を塩漬けにしてマンスールに送り付けた。
マンスールは
「このように恐ろしい男と自分との間に大海をおいたアッラーに讃えあれ」
と叫ぶとともに、
「ただ一人三大陸を巡り、徒手空拳で王国を築く。
彼こそはクライシュ族(ムハンマド一族)の鷹である」と称賛した、と言われている。
アブドゥル・ラフマーンの築いた国は「後ウマイヤ朝」と呼ばれ、
その後200年以上に渡ってイベリア半島を支配する。
ローマ帝国崩壊後に文明の衰微した北方ヨーロッパとは対照的に、
無数の図書館や学校、浴場や庭園に満ち溢れ、
キリスト教徒、ムスリム、ユダヤ教徒が平和に共存する豊かな国だったという。
後ウマイヤ朝の後期になると、アッバース朝の衰退を見て、
王は「カリフ」を称する。
末期のカリフ、アル・ハカム2世は生涯に20万冊の書物を読んだとすら言われている。
しかしカリフがあまりにも読書に熱中しているうちに、権力は彼の手から滑り落ちていった。
宰相が実権を奪ったのはまあいい。彼はとても有能だった。
ところが、宰相の息子がいけなかった。まったくの無能で人望の欠片もない。
極め付けは、祖父がキリスト教徒のナバラ国王だったために金髪をしていたことだった。
「異教徒みたいな奴だ」とブーイングを浴びながら、カリフの位を狙って
無茶なクーデターを起こしたので、反対派が沸き起こり、混乱のなかで後ウマイヤ朝自体が崩壊。
以後のイベリア半島は、国土回復を目指すキリスト教諸国と分裂したイスラーム諸国が
くんずほぐれつの泥仕合を繰り広げることになる。
ムハンマドの娘ファーティマ、そしてその婿であるアリーの末裔を称する
「ファーティマ朝」だ。
ファーティマ朝の起源は、「胡散臭い武装教団」そのものだったが、
10世紀初めに北アフリカ最大の都市チュニスを占領してから爆発的に勢力を拡大。
たちまちエジプトまでを占領し、アッバース朝に残された領土の半分を奪った。
ファーティマ朝はその名前からも察せる通り、シーア派の王朝だった。
それまで日陰の存在だったシーア派が、ついに大国を支配するようになったのだ。
同じ頃、東側でも強力な新興勢力が出た。
イラン北部、カスピ海のほとりに住むダイラム人が建てたブワイフ朝だ。
ダイラム人は早くから精強な歩兵として知られていて、傭兵として暮らしを立てる者が多かった。
そんな傭兵隊長たちのなかに、「ブワイフ」という男から生まれた三人の兄弟がいた。
彼らは協力して自分たちの国を作り、イランを支配した。
権力が確立すれば権威がほしくなる。
945年、三兄弟の一人、ムイッズは大軍を率いてバグダードに「上洛」し、
怯えるカリフから「大アミール」という称号をもぎ取った。
これ以後しばらく、アッバース朝カリフは内にあってはマムルークの神輿、
外にあってはブワイフ朝の傀儡となる。
アッバース革命の翌年、中国の「唐」とアッバース朝がタラス河畔で交戦したが、
これは唐がもっとも西に伸びた瞬間だった。
ところがそれから僅か4年後の755年、唐の本国で異変が起こる。
現在の北京周辺を任されていた将軍、安禄山が反乱を起こすのだ。
帝国副都の洛陽、そして首都長安はたちまち陥落し、皇帝玄宗は四川に逃れた。
唐はこの反乱を自力で鎮定することが不可能で、遊牧民のウイグル族に支援を求めた。
ウイグルの援助で辛うじて安禄山の乱は鎮定されたが、隙を狙ってチベットの吐蕃が挙兵。
長安を一瞬ながら占領し、シルクロードの喉元である河西に進出し、唐と中央アジアの連絡を絶った。
これ以後、唐の国力は大きく低下し、ウイグルと吐蕃が東ユーラシアの覇者となる。
ところが840年にモンゴル高原を大寒波が襲い、大量の家畜が凍死。
ウイグル帝国は見事に崩壊し、モンゴル高原の遊牧民は四方に散っていった。
こうして、この大陸の歴史上で何度目かの「民族大移動」がはじまる。
西に動いたウイグル族に背中を押されたテュルク族は、アラル海周辺、
現在のウズベキスタンを中心とする肥沃な農耕地帯に侵入し始めた。
これを受けて、このあたりの地方政権はテュルク族を傭兵として盛んに起用する。
そのうちに、主人の政権を乗っ取ってテュルク族自身が政権を運営するようになる。
こうしてウイグル帝国崩壊から約100年後、940年にアフガニスタンで「ガズナ朝」が生まれる。
ガズナ朝が最も栄えたのは第5代マフムードの時代だった。
彼は恐るべき征服者で、13回にわたってインドに遠征。
向かうところ敵なく、ヒンドゥー教の寺院を破壊掠奪してまわった。
グジャラートではマフムードの兵士たちが神像を叩き壊したところ、
中から何百年ものあいだ巡礼者たちが寄付した膨大な金銀財宝があふれ出し、
それを戦利品として持ち帰ったために7年間も税を取る必要が無くなったという。
しかしマフムードが世を去る頃、テュルク族の中でも最も強力な部族が姿を見せつつあった。
ガズナ朝はこの新興勢力、「セルジューク族」に大敗した。
セルジュークはその頃登場したテュルクの一部族で、
その後みるみる勢力を拡大する。
そして1055年、セルジュークの族長トゥグリル・ベクは
イラン全土を制圧し、ブワイフ朝を蹴散らしてバグダードに「上洛」する。
いわば桶狭間で大国今川を破り、三好一族を蹴散らして上洛した織田信長のごとし。
トゥグリル・ベクはバグダードでアッバース朝カリフに謁見もとい恫喝して娘を嫁に迎え、
「東洋と西洋のスルタン」という厨二病気味な称号を獲得した。
ちなみに「スルタン」とはアラビア語で「支配者」のこと。
ところが、1063年にトゥグリル・ベクは「鼻血が一向に止まらない」という奇病で死亡する。
アルプ・アルスランはニザーム・アルムルクというペルシア人の文官を宰相にして、
政治一切を任せた。
もとより当時のテュルク人は戦うことが全てで、おそらく文字の読み書きもできない。
これ以後、「テュルク人が戦い、ペルシア人が政治をする」という分業が定着する。
アルプ・アルスランは名将で、西のアナトリア(現在のトルコ)に遠征し、
東ローマ帝国軍を破って皇帝を捕虜にした。
これ以後、アナトリアに大量のテュルク人が移住し、イスラーム国家「トルコ」の淵源となる。
ところが、それからしばらく後。
中央アジアのサマルカンドを攻撃していたアルプ・アルスランは、
捕えた敵将に「ふんぞり返って威張りくさる女みたいな男めが」と挑発されたのに激昂し、
「そいつの縄を解け! 俺が手ずから射殺してやるわ!!」と命じるも、興奮のあまり矢を外す。
二の矢をつがえる暇もなく敵将が切りかかってきて、あえなく非業の死を遂げたという。
バカである。
彼は狩猟が趣味で、政治には全く興味がなかったので、
宰相のニザーム・アルムルクが国政の全権を握ることになった。
ところで、ニザーム・アルムルクにはこんな伝説がある。
彼は若いころ、とある学院で勉学に励んでいた。
その頃、彼には二人の親友がおり、一人はオマル、一人はハサンと言った。
彼らは互いに「いちばん早く出世した者が残り二人を引き立てよう」と約束した。
やがてニザームが宰相となると、約束通り残る二人を招く。
オマルは詩人で学者だったので、天文台の長官となった。
そしてハサンは書記官になったが、彼は実は狂信的なシーア派信徒であり、
シーア派を弾圧するニザームにひそかに敵意を抱いていた。
ある時、王がニザームにある報告書の提出を命じた。
ニザームは「1年かかります」と答えたが、ハサンは「俺なら40日でできますしおすしwwww」と返答。
ハサンは本当に40日で報告書を完成させてしまったので、ニザームは動揺して、
ハサンが発表する直前に原稿をぐちゃぐちゃに入れ替えた。
王の前で発表を開始するもしどろもどろになるハサンに対して、ニザームは「無能wwwww」と嘲笑。
ハサンは憤激して王宮を飛び出し、ひそかに秘密結社を結成。
弟子たちにシーア派の教義と、教敵を暗殺すれば天国へ行けるという洗脳を施し、ニザームを襲撃させた……という。
上記の逸話、検証してみると登場人物たちの年齢差その他からありえないとされているものの、
ニザーム・アルムルクが暗殺されて死んだのは事実。
マリク・シャーが死んだ頃から、たちまち分裂しまくることになった。
そのなかで一応もっとも有力だったのはマリク・シャーの五男のサンジャル。
彼はどうにか分裂したセルジューク諸国を曲がりなりにもまとめ上げるが、
そんななかで見たことも聞いたこともない敵が東からやって来た。
それより少し前のこと。
ユーラシア大陸の遥か東方では、唐帝国が崩壊したあとに五代十国の戦乱を経て、
北には「遼」、南には「宋」という二大国が成立していた。
そのうち遼のほうが、1125年に新興の「金」に滅ぼされる。
そのとき、まるで後ウマイヤ朝のアブドル・ラフマーンと同じように、
「耶律大石」という王族だけが辛うじて西へ逃走し、やがて態勢を立て直し、
金の力の及ばない西方、中央アジアで新しい国を建設する。
「西遼」または「カラ・キタイ」と呼ばれる、あまりに史料が少なく謎に満ちた国である。
1141年、この耶律大石率いる西遼軍が中央アジアのサマルカンド近郊に出現。
セルジューク朝のサンジャルは戦いを挑むも敗走。
セルジューク諸国の分裂はこれで確定する。
西側から別の侵略者たちがやってきていた。
発端はセルジューク朝の西方進出で、東ローマ帝国が危機に陥ったことだった。
東ローマ皇帝アレクシオスは、西方の未開な半蛮族連中を傭兵として使おうと思い立ち、
ローマ教皇に「異教徒どもが聖地エルサレムを脅かしてる件」と連絡する。
これを見たローマ教皇は、その頃ヨーロッパ側でもいろいろとノリノリの時代だったこともあり
「ここは景気よく聖都奪還の大遠征なんてどうよ」と思い立つ。
かくてヨーロッパ各地の諸侯を集めて「我らの大地から異教徒どもを一掃すべし」と宣言。
いわゆる「十字軍」の始まりである。
「十字軍」という狂信もとい宗教的情熱に燃えた集団の来襲は
アナトリアやシリア沿岸のセルジューク諸国の全く予期しないところであった。
不意打ちのような感じでシリア沿岸部はキリスト教勢力に占領され、エルサレムも陥落。
これ以後、エルサレム周辺を維持するキリスト教徒と、
彼らを追い出そうとするイスラーム勢力の泥仕合が開始される。
第一ラウンドはキリスト教側がひたすら押す。
第二ラウンドではイスラーム側が反撃開始。
クルド人の将軍サラディンがファーティマ朝を滅ぼしてエジプトを掌握し、
シリアに攻め上り、エルサレムを攻略する。
これに対してキリスト教側はドイツ・フランス・イングランドの三王連合軍という
豪勢な布陣で挑むも、まともに戦う気が合ったのはイングランド王リチャードのみ。
リチャードとサラディンの派手で華々しいとはいえ、戦略的にほとんど無意味な対決。
力押しはあかんと悟ったキリスト教側は第三ラウンドとして、搦め手からの攻略を試みる。
シリアの敵前に直接上陸するのではなく、敵の本拠地のエジプトに向かったのだ。
ところが主力のフランス軍がエジプトに上陸したところ、
たちまち敵軍に迎撃され、あっけなく国王が捕虜になる体たらく。
(終わらない件)
この時点のイスラーム世界は分裂を極めていた。
インドに進出したイスラーム勢力は、北インドのデリー周辺を支配。
アフガニスタンからシリアにかけてはテュルク系の大小諸国。
イラクには最早誰の傀儡かもよく分からないながら、傀儡であることは確かなアッバース朝。
エジプトはアイユーブ朝。
北アフリカにはアラブ系のこれまた大小諸国。
イベリア半島は後ウマイヤ朝の崩壊後、キリスト教諸国とイスラーム諸国の慢性戦争真っ最中。
そんな中、新星が中央アジアに上り始めていた。
その国は「ホラズム・シャー国」。国王はアラー・アッディーン。
彼は周辺の西遼、カラ・ハン国、セルジューク、ゴール朝などを次々に破り、
イラン高原の半分以上を支配しようとしていた。
ところがその時、さらに東から魔王がやってきた。
魔王の名前を「チンギス・ハン」という。
ウイグル崩壊以来、3世紀ものあいだ分裂し続けていたモンゴル高原は、
1206年に統一された。
統一者は「チンギス・ハン」を名乗る。世界を震え上がらせる魔王である。
魔王は西をさし示した。
そこにはホラズムがあった。
ホラズム軍は魔王の軍隊に接触した途端に溶け去った。
国王アッラー・アッディーンは国を捨てて逃走し、魔王の番犬、ジェベとスブタイがこれを追撃した。
二人の番犬は王を見失うも「行けるところまで行ってみようぞ」と結論し、
カスピ海の周りをぐるりと一周し、まったく無関係のグルジアだのロシアだのを荒らしまわって帰った。
魔王が死亡して安心するのもつかの間、魔王の子や孫もやっぱり魔王だった。
二代目魔王のオゴデイは北中国から東欧までを征服。
三代目魔王のトゥルイは何もしなかったが、四代目魔王のモンケは非常に危険だった。
「世界征服」
世界の歴史上、本気でこれを企図した希少な存在がモンケである。
彼は弟の魔将軍クビライを中国南部、魔将軍フレグをイラン・イラクへ送り出した。
フレグはイランを一瞬で踏み荒らし、バグダードに残っていたアッバース朝をあっさり滅ぼした。
ちなみにこの時、ムスリムの学者たちは「カリフを殺せば世界が滅びます」と脅したが、
キリスト教徒の学者たちは「んなわけないですしwww」と主張したので、後日優遇されたらしい。
魔将軍フレグはそのままシリアに進み、さらにエジプトを窺おうとした。
ところがその時、はるか東の彼方で魔王モンケが急死。
魔将軍フレグは魔風の速さで東へ帰国した。
モンゴル帝国まで来たらイスラーム世界史の半分は消化したことになるので、
とりあえずここまでで、明日残っていたら続けますわ。
最後いい加減ですいませんな。
というか細かすぎるな。
イスラーム世界で女子供が困るのもわかる
常に戦争で男が国に居ねえwww
まず、7世紀にササン朝ペルシアと東ローマ帝国が大戦争を続けているさなか、
突然アラビア半島で「イスラーム」という宗教が誕生し、「正統カリフ」たちの指導のもとで
アラブ族たちが「大征服」を開始する。ササン朝はあっさり崩壊し、東ローマも領土の半分を失う。
アラブ族たちは内乱を経て「ウマイヤ朝」を立てる。
ウマイヤ朝はさらに拡大し、東は中央アジア、西はイベリア(スペイン)にまで達する。
言い忘れていたけど、中世イスラーム世界の地理認識ではイラク・シリアあたりを中央として、
それより東のイラン・中央アジアを「マシュリク」(東方)、北アフリカ・イベリアを
「マグレブ」(西方)と呼んでいた。
ウマイヤ朝ができて100年ぐらいすると、中央アジアで反乱が起こって「アッバース朝」が誕生する。
このアッバース朝は、アラブ人中心のウマイヤ朝とは違ってペルシア人を重用した。
これ以後、イスラームを生み出したアラブ族は、とくにマシュリクではどちらかというと二線級の存在になる。
ところがアッバース朝は広大すぎる領土を統制しきれず、各地で地方政権が成立。
イベリア(アンダルス)の後ウマイヤ朝、北アフリカ(イフリーキヤ)のファーティマ朝は「カリフ」の称号すら名乗った。
東方では9世紀頃からテュルク系遊牧民が流入開始。
最初は傭兵として、のちには征服者としてイスラーム世界の東半分を制覇する。
12世紀頃までには、マシュリクは武人であるテュルク人と文官であるペルシア人が君臨する世界になった。
エジプトより西のマグレブでは依然アラブ系が主流。
ちなみにこの頃までに、イスラームという宗教はウマイヤ朝やアッバース朝の領土をさらに越えて拡大している。
「イスラーム」というのは聖職者がなく、一般的なイメージに反して異教徒を改宗させることにはあまり熱心ではない。
しかしアッバース朝のもたらした平和のもとでインド洋全域に乗り出した交易商人たちや、砂漠や草原を行く隊商たちは
訪れた各地の人々に「イスラーム」という宗教の存在を印象づけた。
とくに西アジアに比べてあまり文明の進んでいない地域(ほとんどどこでもそうだけど)では、
「イスラーム」は文明の象徴として受容される傾向にあった。
13世紀、モンゴル帝国が成立するころまでに、「イスラーム」はサハラ砂漠の南のニジェール流域、
東アフリカの沿岸部、北インドと南インドの沿岸地域、内陸ユーラシアの大草原、南シベリア、
そして中国南部の沿岸地域にまで伝播していた。
テュルク系傭兵が建てたガズナ朝のマフムードは13回もインドに遠征したけれど、
これはあくまで一過性の掠奪遠征に過ぎなかった。
しかしインドの豊かさを知った中央アジアのテュルク人たちは、これ以後本格的なインド進出を目指す。
ガズナ朝に取って代わったゴール朝はデリーまで進出。
ゴール朝が衰えると、配下のマムルーク、つまり軍事奴隷が独立して「奴隷王朝」を築く。
この奴隷王朝に始まる5つの王朝を「デリー・スルタン朝」と呼び、デリーを中心に北インドを征服していった。
もう一つはアフリカ。
サハラ砂漠の南の熱帯地方には、早くからガーナ王国という大国があった。
この地方は砂金や岩塩が豊富で、イスラームが北アフリカを征服すると、多くの商人が来るようになった。
ガーナ王国や、その後に成立したマリ王国の支配者たちは徐々にイスラームを受け入れ、
学者を保護し、学院を立てて本格的なイスラーム国家に変化していく。
時は流れて11世紀。
後ウマイヤ朝とファーティマ朝が衰退してマグレブ(西方)が混沌としはじめる頃。
サハラ砂漠西部のセネガルで「イスラーム神秘主義」という宗教運動が広まり、
武装教団のようなものが結成される。
(ファーティマ朝以来、マグレブではしょっちゅうこの手の武装教団が登場する)
彼らは「アル・ムラーヴィト」と自称し、サハラ砂漠の南北を蹂躙し、
北アフリカの沿岸部を制圧し、さらにイベリア半島に乗り込んでキリスト教徒と激闘を繰り広げた。
それからほどなく、今度は「アル・ムワッヒド」という武装教団が出現。
これも全く同じようにサハラ砂漠の南北を蹂躙し、北アフリカの沿岸部を制圧し、
イベリア半島に乗り込んでキリスト教徒と激闘を繰り広げた。
でもこのあたりの歴史については、東方との関わりも少ないのでこのくらいでいいかと思う。
彼の名はバイバルス。出身は南ロシア。
モンゴル軍がロシア・東ヨーロッパに遠征したときに少年だったバイバルスは捕虜となって、
奴隷商人に売り飛ばされた。
もともと片目だったのでなかなか買い手がつかなかったが、やがてエジプトを支配するアイユーブ朝
(十字軍と戦ったサラディンが建てた国)のスルタン親衛隊に取り立てられる。
奴隷軍人、この頃イスラーム世界各地で盛んに使われていた「マムルーク」だ。
バイバルスはおそろしく体力があって、鎧を着たまま筏を引っ張ってナイル川を泳ぎ渡ったり、
1日で600キロを駆け抜けたあとに平気でポロの試合に出場したりしたらしい。
そんななか、エジプトにフランスの「十字軍」が来襲する。
そのとき折あしく、スルタンは重病で瀕死の状態だった。
やむなく「シャジャル・ドッル」という王妃が国政をとり、マムルークたちが奮闘してフランス軍を破り、国王を捕虜にした。
ちなみにこの「シャジャル・ドッル」ももともとは奴隷出身だった。
シリアに出陣していた王子が急ぎ帰国して王位につくが、彼は奮闘したシャジャル・ドッルやマムルークたちを蔑ろにした。
不満を持ったマムルークたちは王子を襲って殺害する。
ちなみにこのとき何を思ったか、マムルークたちは閉じ込めていたフランス王を引き出して、
彼の目の前でアイユーブ朝の王子を切り捨てたらしい。
フランス王迷惑www
そんなわけでアイユーブ朝は滅亡し、奴隷軍人マムルークたち自身の王国、「マムルーク朝」が成立する。
初代国王はなんとシャジャル・ドッル。
イスラーム史上稀有の女王になった。
シャジャル・ドッルは女王であることに不安を感じたのか、有力なマムルークの武将と結婚し、彼に王位を渡す。
粛清が始まり、ライバルになりそうなマムルークたちは軒並み殺されるか追放された。バイバルスもその一人だった。
1258年。
東方から来た魔将フレグはバグダードを占領し、アッバース朝最後の飾り物のカリフを処刑した。
一説では、カリフが財宝を惜しんで守備兵を雇わなかったことを嘲笑して、宝石庫に閉じ込めて餓死させたとか。
陰険である。
圧倒的に強力な魔軍モンゴルの出現を前に、「十字軍戦争」どころではなくなった。
シリア沿岸で延々叩き合いをやっていたキリスト教徒とムスリムは、揃ってモンゴル軍に降伏。
昨日までの宿敵同士が仲良くエジプトへ進軍を開始することになった。
エジプトが落ちれば北アフリカも落ち、地中海も落ち、世界はモンゴルに征服される。
この危機を前に、祖国を追われたバイバルスは手勢を率いて帰還する。
要はモンゴル軍と同じく、中央ユーラシアの草原出身で、草原の騎馬戦術を知悉している。
おまけにモンゴル兵は「ふつーの遊牧民」が副業で軍人をやっているだけなのに対して、
マムルークたちは、いずれ現れるであろうモンゴル軍に備えて、職業軍人として軍事訓練を繰り返していた。
それでも、魔軍モンゴルはこの時点でほぼ常勝不敗だった。たぶんマムルークたちは絶望的な心境だっただろう。
ところが、ここで変事が起きる。
遠く中国に出陣していた魔王モンケが急死、魔将フレグは次期魔王決定戦に備えて急ぎイランへ撤退する。
あとにはたった1万2千のモンゴル軍が残された。
が、「それでも俺らは無敵だし」と大胆にもモンゴル軍は更に南下を続けた。
そして両軍は、南パレスチナの「アイン・ジャールート」で激突する。
このとき先鋒の将軍だったバイバルスは、モンゴル軍が得意とする囮戦術を使って、
逆にモンゴル軍を罠に引きずり込んで包囲殲滅した。
無敵モンゴル軍は建国以来半世紀を経て、はじめて、白日の下で、完膚なきまでに惨敗した。
魔法は解けた。モンゴルは魔軍ではなく、単なる人間だったことが証明された。
英雄になったバイバルスは帰りの最中にサクッと邪魔な上司を暗殺して、自分が王位につく。
それ以後バイバルスはものすごい活躍を開始する。
内政を整備しまくり、外交を駆使しまくり、外征しまくって、
ついに「十字軍」を事実上すべて叩き出すことに成功。
その後も繰り返されたモンゴル軍の侵攻もすべて撃退した。
バイバルスはあまりに頻繁に遠征したので、「生涯で地球を七周半した」とも言われている。
これ以後、中央アジアからイランまではモンゴル帝国の勢力圏、
シリア・エジプトはマムルーク朝の勢力圏として、両大国が拮抗する情勢となる。
そんななか、中央アジアで突然、歴史の流れを力づくで逆行させる一大英雄が出現した。
彼の名はティムール。
モンゴル系の小貴族の子で、子供のころは羊泥棒なんぞをやっていたらしい。
捕まって足を散々殴られたせいで生涯片足が使えなくなったともいう。
だがしかし、青年になったティムールは中央アジアに東西から様々な野心家たちが攻め込む中で、
次第に頭角を現し、1360年には中央アジア最大の都市、サマルカンドに入城した。
ティムールは全人類の歴史上で、戦場での指揮能力だけで見れば最強の軍人だったと思われる。
彼はこれから東西南北に息つく間もなく遠征し、たった一人でモンゴル帝国の西半分、ユーラシアの三分の一を再統一してしまう。
峻険な山岳地帯も、灼熱の砂漠も、氷雪の荒野も、荒波の蒼海も彼を阻むことはできなかった。
ティムールは、北はシベリア、南はインド、西は地中海までを征服し、抵抗するすべての都市を破壊し、
抵抗したすべての人間を殺し、至る所で頭蓋骨のピラミッドを建設し、そしてあらゆる職人をサマルカンドに連れ帰った。
世界中の美しいものを破壊し、美しいものを作る人間をサマルカンドに集めて、サマルカンドにその美を再現させた。
そういうわけで、現在のウズベキスタンに位置する古都サマルカンドは「中央アジアの真珠」と言われる美都となった。
ちなみにティムールにはいろいろな逸話がある。
たとえば、彼はチェスの達人だった。戦いの前夜には深夜までひとりチェス盤に向き合って、駒を動かしながら作戦を練ったという。
息子が生まれたときにチェスの勝負をしていて、王と城の駒を取ったところだったので、
「シャー・ルフ」(王・城)なんていうDQNネームをつけている。
文字は読めなかったけど何か国語をも理解し、歴史物語を語らせるのが好きだった。
シリアのダマスカスを包囲したとき、ちょうど城内にいた北アフリカの大歴史家イブン・ハルドゥーンを呼び出し、
延々北アフリカの地理について説明させたあと、古代バビロニアのネブカドネザル王が
どの民族だったかという無意味にアカデミックな議論を吹っかけたらしい。
敵に対しては血も涙もない人物だったけれど、部下はとても大切にしたらしい。
毎回サマルカンドを出陣するときに、城門の脇に兵士一人ひとりに石を投げさせた。
兵士たちが次々に出陣するにつれて、城門の脇には石の山ができた。
軍が凱旋すると、今度は兵士たちに石をひとつひとつ拾わせる。
それでも、戦いで死んでいった者たちの数だけの小さな石の山が最後に残る。
ティムールはそれを見て慟哭したと伝えられている。
そんなティムールはえらく年寄になるまで飽きもせず征服戦争を続け、70歳も過ぎてから「次は中国遠征」と号令。
何十万もの馬や羊や山羊を駆り集め、何年もの遠征の準備を整えて真冬に出陣したは良いものの、
寒さのあまり酒を飲みすぎて心臓発作を起こし、行軍中に急死。
ティムールの死とともに一代で築かれた大帝国は崩壊し、歴史の流れはもとに戻る。
元通り、モンゴル帝国の崩壊と分裂というプロセスが再開する。
11世紀後半、セルジューク朝のアルプ・アルスランが東ローマ帝国を破って以来、
アナトリアにテュルク族が続々と移住し始めた話をしたと思う。
当然ながら彼らはムスリムで、セルジューク朝の分裂とともにアナトリア各地にいくつもの小国が成立した。
そんな状況のところ、13世紀の中ごろに遥か東方から「エルトゥルル」という老族長が、
一握りの家畜と一族を連れて流れ着き、「ルーム・セルジューク朝」という地方政権に保護を求めた。
どうやらモンゴル軍の中央アジア侵攻から、命からがら逃げ落ちて来たらしい。
ルーム・セルジューク朝はエルトゥルルに領土の最西端、異教キリスト教の東ローマ帝国と接する地域に小さな領地を与えた。
エルトゥルルは生涯を族長というより羊飼いの長老レベルの人物として過ごした。
エルトゥルルの息子のオスマンはもう少し勢力を拡大した。
時は乱世になりつつあった。
辺境の地では宗教の違いはあまり問題にならない。
その土地ではキリスト教徒もムスリムも混じり合い、気兼ねなく近所づきあいをし、助け合って暮らしていた。
オスマンは冬は平地の町で暮らし、夏に高原に放牧しに行くときは麓のキリスト教の修道院に荷物と女子供を預けたという。
オスマンは夢があった。
彼が知っている世界の中でいちばん大きくて一番輝かしい町、「ブルサ」という丘の上の田舎町を、いつか自分のものにしたい。
オスマンは生涯をかけてこの夢を追い、何年もかけてブルサを包囲し、ブルサ陥落直前に世を去った。
彼が死んだとき、蔵には粗末な衣服と皿と匙、数枚の金貨程度しか残っていなかったという。
このオスマンから、やがて三つの大陸に600年間君臨する「オスマン帝国」が始まる。
東ローマ帝国末期の相次ぐ帝位継承争いのなかで、アナトリアのテュルク系ムスリムたちはしばしば傭兵として使われた。
オスマン一族もその動きに乗って領土を拡大する。
東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルは黒海と地中海を結ぶボスポラス海峡に面する。
海峡の西はヨーロッパ、東はアジア、しかし海峡の幅は泳いで渡れるほどに狭い。
その狭い海峡を隔ててコンスタンティノープルを指呼の間に臨むスクタリがオスマン家の手に落ちた。
ついで帝位継承戦争の援軍として海峡を渡り、ヨーロッパ大陸に進出。勢いに乗って要衝アドリアノープルを占領。
ブルガリアを破り、セルビアを破り、キリスト教徒の騎士たちをも自軍に組み込み、
いつしかオスマン家はちょっとした地域政権になっていた。
1389年、コソヴォの戦いでバルカン半島のキリスト教諸侯連合軍を撃破。
ところがその陣中で、時のスルタン、ムラト1世が刺殺される。
その場に居合わせた王子バヤズィトは直ちに即位し、その後破竹の快進撃を開始した。
バヤズィトは疾風迅雷、神速の用兵を得意とし「雷光王」とあだ名される。
彼の指揮のもとで、オスマン家はバルカン半島の大半、アナトリアの大半を制覇した。
ところが、ここで「第二の魔王」ティムールが登場する。
アナトリア中部のアンカラでオスマン軍とティムール軍が激突。
さしもの雷光王も「第二の魔王」の敵ではなく、大敗を喫する。
バヤズィト自身も捕虜となり、オスマン国家は一時滅亡してしまった。
しかしティムールは遠隔のアナトリアにはあまり興味もなかったうえ、
いずれにせよ間もなく酒の飲みすぎで死亡する。
オスマン家の王子たちは体制を建て直し、国家を再建する。
そして1453年、オスマンの第7代スルタン、わずか21歳のメフメト2世は16万もの大軍を動員し、
一千年間にわたって陥落することがなかった東ローマ帝国の首都、コンスタンティノープルを占領した。
「ローマ帝国」はついに滅亡し、コンスタンティノープルに入城したメフメトは町を「イスタンブル」と改名。
ローマ皇帝の継承者と称した。
オスマン国家は「オスマン帝国」となったのだ。
東ヨーロッパでの勢力拡大には苦労し、モルダビアやワラキア、アルバニアといった小国に最後まで抵抗された。
ちなみに現在のルーマニア南部にあたるワラキア公国を支配していたブラド3世は
オスマン軍の捕虜たちを串刺しにして侵入するオスマン軍を動揺させ、夜襲をかけてメフメト2世の天幕に肉薄した。
のちの「ドラキュラ公」のモデルである。
以上余談。
真に「征服王」というのにふさわしいのは、メフメトの孫のセリム1世だろう。
彼は東のペルシアを破り、シリア・エジプトを征服し、三大陸に広がるオスマン帝国を確立したのだ。
ところでその前に、ティムール帝国崩壊後のペルシア(イラン高原)の情勢を見ておきたい。
イラン高原ではティムール帝国崩壊後、群雄角逐の中で「白羊朝」と「黒羊朝」という二大勢力が台頭していた。
どちらもアゼルバイジャンあたりの遊牧部族で、もちろんイスラームを信じてはいたものの、
昔ながらのシャーマニズムの影響も残っていたのか、白い羊や黒い羊を自部族の象徴としていたらしい。
白羊朝のもとで盛んに蠢動する不穏な教団組織があった。
サフィー・アッディーン・ユースフという修行者が創始したこの教団をサファヴィー教団という。
たびたび白羊朝に弾圧を受けながらも勢力を蓄え、ときに白羊朝と協調して王女を教主の妻に迎えることもあった。
白羊朝が衰えた1499年、わずか12歳だった教主イスマーイールは各地の教徒に檄文を発した。
「今こそ我らの時がきた。決起せよ! 地上の楽園を実現せん!」
天才少年である。
でありながら、十代前半。
10代前半でありながら6000人もの教徒を結集したイスマーイールは、美貌と詩才で荒くれ男たちの心を虜にする。
「教主のためなら命をも惜しまじ!」と絶叫する荒くれ男たちの支持を受け、美少年は14歳にしてタブリーズを占領。
この町で「我らはシーア派の国家を建設する」と宣言し、10代のうちにイラン全土を征服した。
パねぇ天才少年である。
1510年、23歳のイスマーイールは中央アジアのメルヴで、南ロシアから大国を築きつつあった
モンゴル系遊牧民のシャイバーニー朝を破り、敵王シャイバーニー・ハーンの髑髏に金箔を貼って酒杯とした。
イスマーイールは幼いころから自分を神の化身と「本気で」信じていたらしく、いろいろと歪んでいるのである。
この天才美青年と、拡大を続けるオスマン帝国のセリム1世が、1514年にアナトリア東部で激突する。
この時、オスマン軍は大量の鉄砲と大砲を動員し、柵を巡らしてサファヴィー軍を待ち受けた。
イスマーイールはオスマン軍に向けて全軍突撃を指令する。
そのとき、地獄の蓋が開いた。
地響き立てて疾走するペルシア騎兵に向けて、オスマン軍の圧倒的な火力が放射され、戦場は虐殺の巷と化した。
サファヴィー軍は建国以来初めて敗北した。それもどうしようもなく決定的な敗北だった。
かくて青年イスマーイールは初めて理解した。
どうやら自分は神の化身ではなく、ただの人間であったらしいと。
天才青年は人生で最初のの挫折を味わい、それを乗り越えることができずに酒に溺れ、37歳で世を去る。
オスマン軍はタブリーズを占拠したものの、それ以上東へ進軍することはできず、転身してシリア、エジプトに進軍。
かつてモンゴル軍を破ったマムルーク朝の騎馬軍団も新時代の火薬兵器の敵ではなかった。
こうしてセリム1世は、ヨーロッパからアジア・アフリカにまたがる大帝国を建設する。
彼は珍しく「バーブル・ナーマ」という自伝を書き残している。
あるとき風が吹いて一部の原稿が飛んでいってしまったらしいが、それでもとても有益な史料になっている。
さて、バーブルは若いころから中央アジア最大の都市サマルカンドを手に入れようと、同族間の争いを繰り返した。
三度手に入れて三度失い、悟った。
「ムリなもんはムリ」
そのとき、ふと思いついたのが、先祖のティムールが遠征したというインド、山の彼方の豊かな国のことだった。
その頃インドはデリーに首都を置くロディー朝の末期だった。
バーブルは1万程度の軍隊を率いてインドに侵入し、パーニーパットという場所でロディー朝の大軍と遭遇した。
敵軍は小山のような象を大量に動員していた。
バーブルは時代の流行に従って、鉄砲でこれに対抗。象たちは混乱して自軍に突っ込んで自滅。
バーブルは快勝してデリーに乗り込み、北インドの支配者となった。
彼らはティムールの子孫であり、さかのぼればチンギス・ハンの子孫になる。
インドの人々はバーブル一派をモンゴル、訛って「ムガル」と呼んだ。ムガル帝国である。
バーブルは自伝で、インドへの不満を延々と書き記している。
酷熱の気候、長雨と疫病、不潔さ、食べ物、すべてが気に入らなかった。
彼はいつも高燥な中央アジア、サマルカンドのメロンを夢見ていた。
ある時、バーブルの最愛の息子フマーユーンが熱病にかかった。
やはり忌々しいのはインドの気候である。
バーブルは「私の生命を捧げるので息子を救ってください」とアッラーに祈った。
祈りは聞き入れられ、フマーユーンは回復し、建国者バーブルは病死した。
まあ看病中に感染しただけだとも思うが。
フマーユーンはさほど有能ではなかったようで、シェール・シャーという人物に一時王権を奪われて中央アジアに逃げ帰っている。
そこで
ペルシアから来たサファヴィー朝に支援を求め、シーア派への改宗を条件に援軍を得た。
折しもインドではシェール・シャーが大砲の暴発で死亡。
野菜売りから成り上がったヘームーという武将がデリーを押さえるが、こちらはフマーユーンに追い払われた。
デリーを回復したフマーユーンであるが、翌年、書庫の階段で足を滑らせて転落死。息子アクバルが第三代皇帝として即位する。
アクバルはインドに暮らす様々な民族や彼らの宗教を尊重し、融和の姿勢を前面に出した。
異教徒からの徴税を停止し、ヒンドゥー諸王の娘たちを妻とする。
インドではムガル帝国のもとで、イスラームとヒンドゥーの融合した独自の文化が繁栄した。
ペルシア語で「世界を掌握する者」という意味の名前だが、実際には彼はそんなに覇気のある人物ではなかった。
即位前の彼は反抗的で、二回謀反を起こして二回許されるも、二回目には父アクバルに平手打ちをされたという。
謀反を起こしながら平手打ちで済むとは寛大な話である。
即位後には、ある商人の未亡人(29)に一目惚れし、4年間も求愛を続けてめでたく彼女(33)を手にした。
ジャハーンギールは彼女に「ヌール・ジャハーン」(世界の光)という名前を与え、
彼女が非常に有能だったので、彼女とその一族に国政をすべて任せて毎日昼寝して暮らしたという。
ある時、冬に狼が遠吠えするのを聞いて、「山の狼が寒がっているから誰か服を持っていってやれ」と命じた逸話が残る。
ジャハーンギールの次はシャー・ジャハーン。「世界の王」を意味する名前だが、彼も似たり寄ったりのヒモ男であった。
最初は娘を政治顧問にし、次には王妃のムムターズ・マハルに政治を任せ、やはり昼寝をして日々を送る。
ムムターズ・マハルが死んだとき、嘆きに嘆いて彼が作らせたのが、かの霊廟「タージ・マハル」である。
アクバルの融和政策を弄ることはなかった。
ところが第5代として即位したアウラングゼーブは父や祖父よりはるかに有能で覇気のある君主だった。
彼は父、シャー・ジャハーンが重病になったとき、いち早く兵をあげ、各地の兄弟たちを尽く打ち破って殺す。
そのとき、父シャー・ジャハーンが奇跡的に重病から回復したという知らせが入った。
今更回復されても困るので、アウラングゼーブは打ち破った兄の生首を父の食卓に送り付ける。
当時デリーに居合わせたイタリア人の記録によれば、シャー・ジャハーンはこれを目にして絶叫し、
頭をテーブルに打ち付けて失神したという。
アウラングゼーブは失神した父を強制退位させて帝位につき、
父が死ぬまで「兄ばかり大事にして俺のことは見向きもせんで許せんわ」とネチネチと手紙を書き送ったという。
このようにしつこく執念深い性格のアウラングゼーブは、同時に狂信的なムスリムで、
インド全土を制覇し、イスラームを徹底することを目指していた。
帝国に従属していたヒンドゥー諸侯たちからの徴税を再開し、異教徒を圧迫し、
反抗する者は圧倒的な力で押しつぶした。
全土制圧のために南インドに大軍を送り、埒が明かないと見るや自ら都を捨てて前線に移る。
ちなみに、インドの人口構成上、その軍隊のほとんどがヒンドゥー教徒だったという事実は
深く追求すべきではないだろう。
1681年以降、アウラングゼーブは死に至るまで26年間も陣頭指揮を執り続け、二度と都に帰らなかった。
その甲斐あって一瞬ムガル帝国はインド亜大陸全土を統一したものの、たちまち各地で反乱が発生。
険しいデカン高原で無数のゲリラをもぐら叩きのように叩いてまわるなかでアウラングゼーブの後半生は過ぎていった。
1707年、アウラングゼーブは88歳という高齢で妄執の生涯を終える。
死の直前、彼は「余は愚かであった」と心底の後悔を書き残しているが、すでに遅かった。
アウラングゼーブが都を遠く離れた辺境の陣営で死去したとき、ムガル帝国はすでに崩壊していた。
ウマイヤ朝の大統一(7~8世紀)
アッバース朝の大統一(8~9世紀)
混乱状態(9~10世紀)
テュルク族の西進(10~12世紀)
モンゴル帝国vsマムルーク朝(13世紀)
ティムール帝国(14世紀)
と来て、15世紀の後半からは
オスマン帝国、サファヴィー朝ペルシア、ムガル帝国
という三大国がイスラーム世界に並立することになる。
書き方としてムガル帝国だけ先に片付けたので、次はオスマンとペルシアの続きか。
もはや見てる人いなさそうだわ。
実は近代はそこまで詳しくないという
さて、オスマン帝国の続き。
セリム1世の後を継いだのはスレイマン1世。後の世では大帝と讃えられる。
といって、彼が何をしたかというのはちょっと難しい。
法典を整備して、十数回遠征したけど、ハンガリー征服以外はセリム以上に目立って領土を広げたわけではない。
地図上では彼の時代にオスマン帝国領は北アフリカをアルジェリアまで大拡大しているんだけど、
これは、このあたりの豪族や海賊が自分から帰順してきただけであり。
スレイマン大帝の事業でいちばん有名なのは第一次ウィーン遠征。
オスマン帝国はハンガリー征服後、中央ヨーロッパの大国ハプスブルク帝国と接触した。
その首都であり、西ヨーロッパの入り口というべき要衝、オーストリアのウィーンは
オスマン帝国の人々にとって「赤い林檎の国」といわれる憧れの場所だった。
なんで赤い林檎なのかは知らん。
スレイマンはウィーンを包囲するも、イスタンブルからここまで来るのに時間がかかりすぎ、
冬が迫ったので雪が降る前に撤退。
オスマン帝国の拡大の限界となった。
それとは別にスレイマンは艦隊をフランスのマルセイユや東南アジアのスマトラまで派遣したり、
中央アジアのブハラに援軍を送ったり、ドイツの宗教改革運動に介入したりしている。
スレイマンが何をしたのかというのは難しいけど、彼の時代のオスマンがまさに全盛期で、
その影響力がユーラシア大陸の多くの地域まで及んだのは間違いない。
休憩。
金閣湾を封鎖されたので、船を丘超えさせたとか
スレイマンの功績は中央集権化をほぼ完成させたことだね
スレイマン以降スルタンは形骸化し、宮廷出身の軍人政治家が政治の実権を握りそれを官僚機構が支えた
オスマントルコで面白いのは、政治の実権を握っていたのがイスラム教徒のトルコ人ではなく、被征服地のキリスト教徒の子弟たちだったこと
彼らは、徴用された被征服地のキリスト教徒の農民の子だったり捕虜となった旧支配者の子で、「スルタンの奴隷」と呼ばれた
イスラムに改修させられたのち徹底したエリート教育を授けられて、スルタン直属の常備軍(イェ二チェリ)を担ったりスルタンの側近として宮廷に入った
大宰相、宰相たちはみなこの「スルタンの奴隷」出身
故郷が征服されたと思ったら、帝国内部で立身出世の道が拓けるんだから人生はわからんもんだね
でも徴用される条件が、身体壮健、頭脳明晰、眉目秀麗だってさ
>>98
あー、それ書くべきだったね。
コンスタンティノープルの内港である金角湾に面する城壁は低いからと艦隊を無理やり丘越えさせたんだけど
残念ながら決定打にはならなかった。
現地歩いたことあるけど、丘というより小山に近い高さ&傾斜。
>>101
補足どうも。
>>96の「カーヌーニー」、つまり立法者を意味する異称の通り、スレイマンの時代に中央政府の機構はほぼ整った。
当時のオスマン帝国の政府と軍隊はおそろしく統制さえていて、ヨーロッパ人の記録だと
「衛兵があまりに身動きしないので置物かと思った」とか書いてある。
政治面でも大臣たちの御前会議で物事がサクサク進むようになって、スルタンは中二階の格子越しに
姿を見せずに会議を見下ろしているだけでよかった。
そのうち「見下ろしてなくてもバレないじゃん?」とスルタンが気づいてしまったのが、
オスマン皇帝無能化の第一歩だった。
>>102
それがこの国の面白いところで、だから中央政権の構成者たちは自分たちを「トルコ人」ではなく
独自の「オスマン人」という民族だと認識していたらしい。
スレイマン大帝晩年の大宰相ソコルル・メフメト・パシャもこのデウシルメ制度で徴用されたんだけど、
彼の実弟は徴用対象にならず、故郷で出征してやがて地元の大主教にまでなっている。
「アラビアの夜の種族」って小説はやっぱり嘘くせぇいい加減だなって
感じなのかなあ。著書は確か古川日出男?って名前だったかな?
西から地中海世界の半分とアラビア半島を押さえるオスマン帝国。
スンナ派最大の国家であり、推定2500万の人口を擁する。
スルタン親衛隊のイェニチェリ、封建騎兵スィパーヒを擁し、その軍事力は世界でも一二を争う。
イラン高原から中央アジアにかけてはサファヴィー朝ペルシア。
タブリーズ、のちにイスファハーンを都とし、シーア派を国教とする。
「キジルバシ」(紅帽の徒)と言われる勇猛な騎兵を擁するも、
彼らはしばしばシャー(国王)の権威を無視して横暴に振る舞ったため、やがて粛清の運命を辿る。
インド亜大陸北部にはムガル帝国。
モンゴル帝国の末裔であり、ペルシアの強い影響を受けつつも、インド在地の文化と混交した
ウルドゥー文化を花開かせる。
人口は推定1億に近いが、その多くはヒンドゥー教徒が占める。
ムガル帝国の実態は各地のヒンドゥー諸侯国の盟主のようなものだったが、
やがて第6代皇帝アウラングゼーブがヒンドゥーの圧迫とインド全土の統一を目指して
強引な統治を展開し、帝国は負担に耐え切れず瓦解への道を歩む。
これから、これら三大帝国の没落と、イスラーム世界のみならず、
非ヨーロッパ世界すべてにとっての長い敗北の物語が始まることになる。
>>109
それは言及しなかったけどセルジューク朝やマムルーク朝の制度だね。
テュルク系遊牧騎兵に領地と徴税権を与えるかわりに軍役の義務を課す。
まあ大雑把にいえばよくある制度。
前期オスマン帝国はイクター制を発展させたティマール制を導入し、
ムガルは領地ではなく俸禄と軍役を結び付けたマンサブダール制や
ジャーギールダール制が用いられた。
サファヴィー朝はもっといい加減な封建制だったので国家統制に苦労している。
>>110
ファンタジーとしてはとても面白いし、渋いネタ使ってると思う。
イスラーム世界の前に強大なライバルとして登場することになる。
ローマ帝国崩壊後、古代地中海世界の統一はやぶれ、地中海の北側と南・東側は異なる歴史を歩むことになった。
地中海の南と東は7世紀以降、イスラーム世界に組み込まれ、繁栄した。
北側の文明は衰微した。
激しい民族移動、広大な未開の森林、貧弱な土壌。
地中海の北側はユーラシア大陸のなかでも最も後進的な地域の一つとして、なかば孤立する。
しかし千年の時が過ぎるうちに、徐々に農業生産力が向上し、商業が興隆し、
キリスト教を共通の価値観とする「ヨーロッパ」という文明が芽生える。
イスラーム世界は、なぜか地中海の北側にはほとんど関心を持たずに来たらしい。
あまりに貧しく未開であるとともに、この地域が強く排他的な文化を築いていたからかもしれない。
しかし、そんなヨーロッパとイスラーム世界が直接接触する地域もいくつかあった。
ひとつは東ローマ(ビザンツ帝国)、ひとつは「十字軍」によって占拠されたシリア沿岸、
そしてひとつは地中海中央のシチリア島、そしてひとつはイベリア半島。
イスラーム世界では、イベリア半島のことを「アンダルス」と呼んだ。
「アッラーが世界を創造したとき、アンダルスは穏やかな気候、豊かな大地、美しい女性など、
多くの恵みを願った。アッラーはそれらをすべて与えたが、それではあまりにもアンダルスへの
恵みが多すぎると思い直し、ただ一つ、「平和」だけを取り上げた」という伝説がある。
アンダルスは大いに栄えたが、後ウマイヤ朝の滅亡後、ここは「タイファ」と呼ばれる
イスラーム系の太守たちと、北から国土回復を目指すキリスト教諸国との長い戦いの舞台になる。
大きく見れば711年から1492年まで続いたこの戦争を、キリスト教側は
「レコンキスタ」(国土再征服戦争)と呼んだ。
キリスト教側は集合離散を繰り返すうちに、やがて「ナバラ」、「レオン」、「アラゴン」、
「カスティーリャ」「ポルトガル」という5つの王国にまとまっていく。
11世紀以降、タイファ諸国はアフリカ大陸から援軍として、
強大なムラーヴィト朝とムワッヒド朝を相次いで呼び込んだ。
窮地に立たされたキリスト教諸国は、「十字軍」の名のもとに大連合軍を組んでこれに挑む。
そして1212年、「ラス・ナバース・デ・トロサの戦い」に圧倒的な勝利をおさめ、
ムワッヒド朝をイベリア半島から撃退することに成功した。
そして15世紀後半になると、数多くのタイファ諸国は淘汰され、
ただ半島南端にグラナダを都とする「ナスル朝」だけが残った。
ナスル朝は何世代もかけて、グラナダに想像を絶するほどに典雅な宮殿を造営した。
夕暮れに赤く染まる丘の上の宮殿は、アラビア語で「赤」を意味する「アルハンブラ宮殿」と呼ばれる。
キリスト教諸国の統合はさらに進んだ。
ナバラはフランス王国に半ば取り込まれ、カスティーリャはレオンを併合して半島中部を押さえた。
そしてカスティーリャ王国の女王イサベルとアラゴン王国の国王フェルナンドが結婚したことで、
イベリア半島の三分の二が事実上ひとつの国になった。
1482年、700年にわたったレコンキスタの最終決戦がはじまった。
北から押し寄せるカスティーリャ・アラゴン連合軍の前にナスル朝の要塞は次々に陥落し、
そして1492年1月1日、最後のグラナダ王ボアブディルはグラナダを開城した。
かくてカスティーリャ・アラゴン両国はイベリア半島からイスラーム勢力を一掃し、
一体化して「スペイン王国」(エスパーニャ王国)となる。
これはイスラーム世界の歴史上で最初の後退だった。
クリストバル・コロンという甚だ胡散臭い詐欺師のような風体の男が、
歴史的大勝利に浮かれるイサベル女王を煽ててうまいこと資金を引き出し、
「西の海を越えていくとアジアに到達する」という自分だけしか信じていないような妄想を実現すべく
船員たちのクーデターをもものともせずに強引に世界の果てに向かって航海した結果、
なんと世界の果ての向こう側に広大な未知の大地があることが判明したのだ。
象徴的でもある。
それまで「世界史」はユーラシア大陸を中心に動いていた。
これからは大洋こそが世界史の軸になる。
であれば、大陸中央部を占めるイスラーム世界から、大洋の岸辺に位置するヨーロッパに
歴史の主導権が移っていくのも当然だったのかもしれない。
さらにスペインは二世代にわたる婚姻政策の結果、イタリア半島を押さえ、
さらにドイツの神聖ローマ帝国と同族化する。
「ハプスブルク帝国」の誕生である。
イベリアからイタリアに及ぶ領土を得たハプスブルク朝スペイン帝国は、
必然的に地中海の残る領域を支配するオスマン帝国にとって最大の敵対者となる。
その形成が完成したのはスレイマン大帝の頃だった。
この時期、スレイマン大帝治下のオスマン帝国は宗教の違いを越えて、スペインを共通の敵とするフランスと同盟している。
しかし二度目の決戦、1571年の「レパントの海戦」はヴェネツィア共和国と結んだスペインの大勝となった。
ただし、これをもってオスマン帝国の衰退が始まったというのは正しくない。
この時点では、レパントの敗戦はオスマン帝国にとって僅かなつまづきに過ぎなかった。
スレイマン大帝死後のオスマン帝国が衰退を開始したといわれることも多いが、それも正しくない。
これからしばらく、オスマン帝国は「全盛状態」を維持する、いわば「国力の高原状態」を続ける。
しかしその時代、帝国の実権を握ったのは皇帝ではなく、後宮の女性たちや大宰相たちだった。
たとえば、スレイマン大帝の死後はもはや皇帝が陣頭に立つことは全くなくなる。
次第に御前会議の場からも皇帝の姿は消え、大帝の晩年に完成した精緻な官僚制が半ば自動的に
帝国をスムーズに運営するようになっていく。
当時のヨーロッパ人は、このオスマン帝国の官僚制を驚嘆と憧れの目で見つめていた。
>>116
代々木上原とか
彼らはインフレや民衆反乱、ペルシアの動乱といった危機をうまく乗り越えて、
帝国の政治制度をさらに整備していき、実はオスマン帝国史上で領土が最も広がったのもこの時代だった。
ところが、1676年に大宰相に就任したキョプリュリュ家の一族、カラ・ムスタファ・パシャは、
1683年にハンガリーの反乱を機に、16万の大軍を召集してオーストリアのウィーンを包囲する。
スレイマン大帝の栄光再現を夢見たらしい。
ところが9月13日、突如ウィーン北東のカーレンベルク山から、当時欧州最強をうたわれた
ポーランドの「有翼騎兵軍団」が怒涛のように突撃を開始。
不意を突かれたオスマン軍は総崩れとなり、「第二次ウィーン包囲」は大敗北に終わった。
強権を揮った大宰相も結局のところ皇帝の下僕でしかない。
カラ・ムスタファ・パシャは帰途に絞首刑となった。
これ以後、オーストリアのハプスブルク帝国を中心に、中央ヨーロッパ諸国による
猛反撃が始まる。「大トルコ戦争」である。
16年間にわたる激戦の末、1699年に結ばれたカルロヴィッツ条約により、
オスマン帝国はハンガリー全土を失った。これこそ、オスマン帝国の長い下り坂の始まりであった。
ちなみにウィーンを包囲していたオスマン軍は陣営の撤収をする余裕もなく敗走していったのだが、
戦後にオスマン軍の陣地を検分していたオーストリア人たちは、ある天幕で謎の黒い塊を発見する。
これがヨーロッパに「コーヒー」が広まるきっかけであった。
もうひとつ。
オスマン軍が敗走していったウィーンでは、奇跡の勝利を祝ってとあるパン屋が
オスマン軍の軍旗をかたどった三日月形のパンを売り出した。
「クロワッサン」の起源である。
休憩。
三大帝国の残るひとつ、サファヴィー朝ペルシアは最も存続期間が短く、この頃には滅亡を前にしていた。
1514年、初代シャー(国王)のイスマーイールが東部アナトリアのチャルディラーンで
オスマン帝国のセリム1世に致命的な大敗北を喫して若くして世を去ると、
「キジルバシ」(紅帽の徒)と呼ばれた騎兵軍団が実権を握るようになった。
第2代シャーのタフマースプ1世が死ぬと完全な無政府状態と化し、オスマン帝国やシャイバーニー朝が盛んに侵入した。
この危機のさなか、冷酷非情な王子アッバースが立つ。
彼は即位するとキジルバシ軍団を強制的に解体し、オスマン帝国の親衛隊イェニチェリを参考に
グルジアやアルメニアのキリスト教徒を徴用した「奴隷軍団」や、銃兵・砲兵を整備する。
これでもってアッバースは国土回復のために奔走し、東西の敵国を退けるとともに、
オスマン帝国の背後に位置する西欧諸国との同盟も模索した。
この頃、ロバート・シャーリーというイングランド人の商人がアッバースに軍事顧問として仕えている。
アッバースは旧都タブリーズを捨てて、イラン高原の中央に位置するイスファハーンに遷都した。
イスファハーンは繁栄を極め、「世界の半分に匹敵する」とまでいわれるようになる。
こうした功績から、アッバースはオスマン帝国のスレイマン1世のように「大帝」と称されている。
しかしアッバース大帝がなまじシャー(国王)の権力を絶対化してしまったために、
彼の死後に無能・無気力・アル中・ヤク中なシャーが相次ぐと、サファヴィー朝は急速に衰退する。
オスマン帝国がハンガリーを失ったのと同じ頃から、サファヴィー朝では部族反乱が頻発するようになる。
とくに東方の山岳民族、アフガン人の首領ミール・ヴァイスの反乱には手が付けられなかった。
1722年、ミール・ヴァイスの息子マフムードが率いるアフガン人が来襲した。
彼らはあまりにも貧しかったので軍馬を持たず、牛に乗って攻めてきたらしいw
しかし、サファヴィー朝はそんな連中にすら抵抗する力が残っていなかった。
イスファハーンは開城し、サファヴィー朝ペルシアは事実上滅亡した。
おまけに西のオスマン帝国と北のロシア帝国が介入。
サファヴィー朝の復興を目指す勢力もあり、ペルシアは混沌とした情勢になる。
最終的に勝利を収めたのは「ナーディル・クリー」という一代の英傑だった。
後に「ペルシアのナポレオン」とも、「最後の中世的英雄」ともいわれる、残虐にして勇猛な人物だ。
ナーディルはアフシャール族という小さな遊牧部族の出身で、若いころのことはよくわからない。
奴隷だったという説もある。
イスファハーンの陥落後、アフガン人の追跡から逃れたサファヴィー朝の王族が落ち延びてきた。
ナーディルはこれを利用し、サファヴィー朝復興を唱えてアフガン人を放逐した。
イスファハーンの回復後、彼は摂政の地位に就くが、もともとサファヴィー朝を
真面目に復興させたかったわけではない。
あっさり傀儡のシャーを放り出して、自ら王位について「ナーディル・シャー」を名乗った。
「アフシャール朝ペルシア」の成立となる。
ナーディルを一言で表現すれば「軍事的天才」。
向かうところ敵なく、ロシア、オスマン帝国を撃退してメソポタミアを奪い、
転じてアフガニスタンに攻め込み、勢いにのってインドまで進撃。
アウラングゼーブの圧制を経て弱体化していたムガル帝国の都デリーに突入して、
世界最大のダイヤモンドだのムガル皇帝の玉座だのをかっぱらっていった。
(ちなみにこのダイヤモンドは現在、イギリスの王冠にくっついてる)
ただ、ナーディルは極めて粗暴で冷酷だった。
反乱を起こした者や敵対した者は容赦なく虐殺し、陰謀を企んだ罪で
自分の息子の目を潰して盲目にしたこともある。
常勝不敗の上に残虐非道。
「マジでこいつ、どうにかせんと……」
ナーディルに対する恐怖が広がり、ついに彼は側近の手によって暗殺される。
じゃんじゃん。
それをある程度まとめたのは、ナーディルの旧臣の「カリーム・ハーン」という人物だった。
彼はイラン南部を統一し、「ザンド朝」という王朝を興す。
アッバース大帝以来の「強くて残虐」パターンの例外で、現代イラン人の歴史認識的には、
わりと心優しい人物だったという評価である。
ちなみに「アフマド・シャー・ドゥッラーニー」という武将がいた。
彼はナーディル・シャーが死んでアフシャール朝の時代が終わると見るや、
沈む船から逃げ出すネズミのごとく、手勢を率いてさっさと故郷に帰った。
そしてアフガニスタン南部のカンダハルを占領して、アフガン諸部族をまとめあげ、
「ドゥッラーニー朝」という王朝を建てる。
「ドゥッラーニー」というのは、当地のパシュトゥーン語で「真珠の時代」を意味するらしい。
アフマド自身は「真珠の中の真珠」という、意味不明な称号を名乗っている。
アフガニスタンは山国だから真珠の希少価値が高いんすかね?
アフマドの直系子孫がずっと続いたわけではないけど、ドゥッラーニー部族連合による王朝という意味では、
この王朝は1973年まで続いていたりする。
「現代」が視野に入りつつある。
>>125
ですな。
北方の雄、当時はピョートル大帝の時代。大国ロシアが目覚めつつある頃合い。
次なる時代の主役は「アーガー・モハンマド・シャー」。
この男、ナーディル・シャーに倍する残虐非道にして凶悪無比な梟雄と伝えられる。
アーガーはカスピ海南岸の「ガージャール族」という遊牧民の族長の子として生まれた。
が、彼が少年のころ、ガージャール族はアフシャール朝に征服され、彼自身は捕虜として去勢されてしまう。
この恨みが彼の中に世界全般への憎悪を植え込んだとみられる。
カリーム・ハーンの時代が来ると、彼はカリーム・ハーンの宮廷があったシーラーズに連行されたが、
ここではカリーム・ハーンに大変寵愛され、さまざまな学問を授けられたという。
だが、カリーム・ハーンが死ぬと、動乱を見越して翌日に彼はシーラーズから逃亡した。
故郷に戻ったアーガーはガージャール族をまとめあげ、イラン高原の覇権争いに加わった。
1794年にはザンド朝を滅ぼし、ケルマーン地方に逃亡したザンド朝の王を追跡する。
そして、この大恩あるカリーム・ハーンの遺児をひっ捕らえるや、カリーム・ハーンが隠した
(とアーガー・モハンマドが妄想した)財宝の在り処を聞き出すために、
頭の上から煮えたぎった油をぶっ掛けたあとに両目を潰すという挙に出ている。
ついでにケルマーン地方の成年男子2万人もセットということで両目を潰されたらしい。
意味不明なレベルで残虐である。
とはいえアーガー・モハンマドは有能ではあった。
グルジアに進軍してロシアの影響力を排除し、ついでにグルジア人数千人を奴隷にする。
そしてイラン全土を平定した1796年に、イラン高原の新しい政治的中心として選び出した
エルブルーズ山脈南麓のテヘランにて即位する。いうまでもなく現代イランの国都である。
アーガー・モハンマド・シャーは世界の歴史上おそらくただ一人、去勢された王朝建設者であった。
そのため当然ながら実子はない。彼以後のガージャール朝諸王は、彼の甥の子孫である。
さて、アーガー・モハンマド・シャーは即位の翌年、ロシアの南下に対処するため、カフカス地方に遠征した。
その途上、自分の居室で二人の召使が喧嘩をしているのを目撃し、激怒して召使に死刑を宣告するが、
部下のとりなしでその召使を許し、そのまま自分の身の周りの世話を任せた。
残虐にして傍若無人なアーガー・モハンマド・シャーは、弱者の恐怖心というものが想像できなかったのか。
アーガーの気が代わることを恐れた召使は、その夜、眠るアーガーを刺殺した。
もっとも、「ガージャール朝ペルシア」自体はアフシャール朝やザンド朝とは違い、建国者の横死後も続いた。
この王朝は専制的でありながら西洋列強の圧迫には弱腰として、イラン人の歴史的評価は低い。
それでも、ガージャール朝の命運は20世紀まで続くことになる。
ここでもまた、「現代」が視野に。
今夜はここまでで。
1800年位っていうと日本の元禄時代か
つい最近のことなんか
1800となると寛政年間で、伊能忠敬が蝦夷地を探検してる頃だね
ペルシアと同じように、ロシアの南下に備えて
>>137
>>139が有力説だったと思う。あとは雪対策もあるかな。
建築様式としてはビザンツ建築がイスラーム建築とロシア建築の両方に影響を与えているという感じ。
>>141
知っている限り、これまで言及してきた人物たちのうちで、ハールーン・アッラシードと宰相ジャアファル、
ウマイヤ朝のハッジャージュとマムルーク朝のバイバルスはアラビアンナイトに登場するよ。
『イスラーム生誕』は高校時代に買って読んだよ。たぶんほかにも読んだ著作あると思うけど思い出せない。
あと、もちろん彼が訳した岩波文庫のコーランも。文体が格好いい。
>>140
トゥール・ポワティエの戦いとかかな。
歴史的にあまり重要とは思わないので書き落としたけど、
あとから有名な戦いだからやっぱり言及しとけばよかったと思っていたところ。
711年4月29日、ウマイヤ朝の将軍ターリク・イブン・ズィヤードは、のちに「ジェベル・アル・ターリク」
すなわち「ターリクの岩」、訛って「ジブラルタル」と呼ばれることになる場所からイベリア半島に上陸した。
迎え撃つ西ゴート王国最後の王ロドリーゴは、グアダレーテ河畔にて壮烈な戦死を遂げる。
かくてアラブ軍は破竹のごとく進撃し、わずか7年でイベリア全土を制圧した。
その後、ウマイヤ朝のアンダルス総督アボドゥル・ラフマーン・アル・ガーフィキーは、
さらに北方のガリア、後にフランスと呼ばれる地域へも進出を開始した。
彼は最終的に地中海北岸を経由して、東ローマ帝国の首都コンスタンティノープルまで
到達しようと目論んでいたという説もあるが疑わしい。おそらくは大規模な掠奪遠征であったろう。
その頃、ガリアを支配していたのはメロヴィング朝フランク王国。
しかし王家はすでに名目化し、王国はネウストリアとアウストラシアの二地方に分裂する兆しを見せていた。
そしてアウストラシア最大の実力者が、宮宰(マヨール・ドムス)なる役職にあったピピン2世と、
その子カールであった。
732年、ガリア西部に侵攻したガーフィキーはボルドーを破壊し、トゥールのサンマルタン教会に
莫大な財宝があるという噂を聞きつけて、軍をさらに北方へ向けた。
ときにアウストラシアの宮宰であったカールは、報を聞くや直ちに迎撃へ向かう。
両軍はトゥールとポワティエの中間にて遭遇し、1週間にわたって対峙。
ついにアラブ軍が突撃を開始するが、フランク軍の重装騎兵はこれを固く拒んだ。
日没が迫り、利あらぬと悟ったアラブ軍は撤退。翌朝、戦場に指揮官ガーフィキーの遺体が発見された。
カールはこの戦いで大槌をふるって奮戦したというので、槌を意味する「マルテル」を冠して
「カール・マルテル」と尊称され、キリスト教世界防衛の英雄として名声を博する。
彼の孫が、カロリング朝フランク王国のカール大帝である。
とはいえこの戦い自体にどれほどの歴史的意義があったかは疑わしい。
当時、キリスト教側とイスラーム側の小競り合いは絶え間なくあったし、その後もイスラーム側は
南フランス沿岸のナルボンヌやカルカッソンヌを占有し、アルプスの山間やリグリアの岸壁に
「アラブ監視砦」が並ぶ時代がしばらく続くのである。
読みやすいし
本スレが未完なので中編(後編かもしれない)は明日の午前(もしかして午後)あたりにまとめます。(転載元:http://open02.open2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1405776434/)
「1がイスラーム世界の歴史についてダラダラ解説」
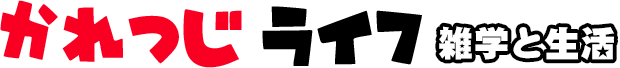
ぶたにくおいしい